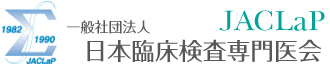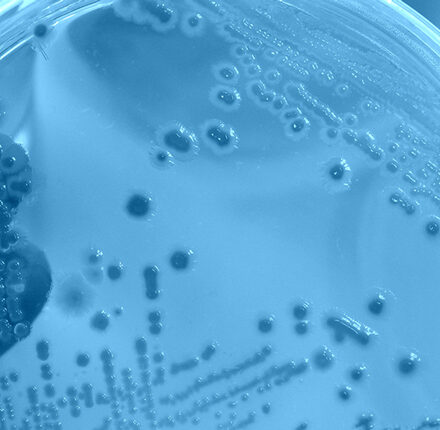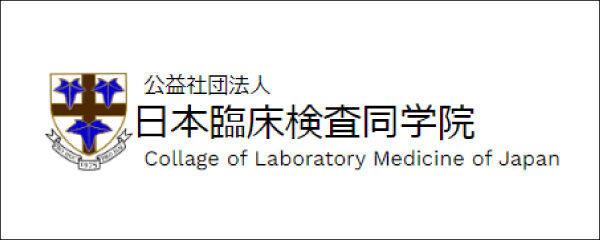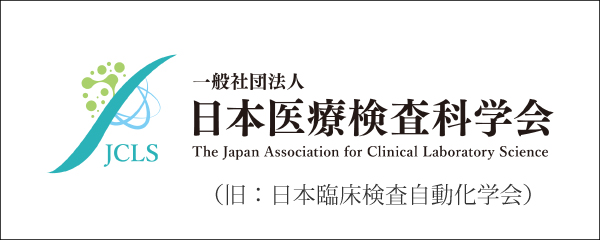臨床検査医学への提言 第九回 渡辺 清明 先生

「実なき学問は先ず次にし、専ら勤むべきは人間普通日用に近き実学なり」
慶応義塾大学名誉教授
渡辺 清明
は じ め に
私は元々血液内科医であり臨床検査の仕事はあまりしていなかった。しかしその後、45歳になった1985年に中央臨床検査部(以下中検)の副部長になり、1991年に臨床検査専門医の資格を取得し、臨床検査の仕事をするようになった。そこで感じたのは臨床検査がその価値をきちんと国民に評価されていない事であった。従って、臨床検査医の役割はその価値を少しでも上げる事だと思った。
その後たまたま、1995年6月に医学部中検教授および検査部長に就任したので、微力であるが、個人的に何をしたかを以下述べる。一人の臨床検査医の生き様として参考にして頂ければ幸いである。
検査部の運営に関して
当時検査部運営の全ては検査部長の責任であったので、約120名の臨床検査集団を日々管理し、年間延べ一千万件を超す検査を施行し、質の高い検査結果を医師や患者さんに還元する作業は膨大であった。
臨床検査の病院収入は医療費の7−8%を占め、当時の慶応病院の総収入は年間300億円程度であったので、20~25億程度あった。まさに大学教授と言っても、教育、研究よりも病院業務や職場管理が中心の仕事になった。
業務では、組織内の方々と共に、組織再編成(ルチン検査と特殊検査を分離)、遺伝子検査室設置、病院内の検査オーダーシステムの簡略化、医師のための臨床検査相談室の設置、外来採血室の設置、診療前検査の導入、病棟の患者さんの採血システムの構築、検査室内の自動搬送システムや新コンピューターシステム稼働など数々の新規検査業務を導入した。
研究面では遺伝子検査グループを構成し、検査部内の医師や検査技師のために研究費を集め、多くの検査関連学会への発表や論文投稿をして貰った。その他コンピュータによる血液細胞画像診断システムの実用化及び遠隔画像診療支援技術の研究、AI による血液疾患の検査診断の開発なども行った。
教育面では、医学生へのポリクリ(実地教育)の開始、臨床検査医学修士制度の構築および大学院の設置などを行った。
検査部以外で対外活動
対外的な活動も大変であった。臨床検査は医療費の約10%を占めるにも拘わらず、専門医は当時は全国で500名に満たず、大変少なく、特に東京にある大学教授には多くの公的職務や学会役職が集中した。ちなみに私の拘わった対外的な職務は下記である:
日本臨床検査医学会理事長、日本検査血液学会理事長、日本臨床検査専門医会会長、日本臨床化学会監事、日本臨床検査自動化学会編集委員、日本臨床病理同学院監事、日本臨床検査標準協議会(JCCLS)会長、The International Society for Laboratory Hematology Board Member、米国臨床検査標準協議会(NCCLS)Board Member、臨床検査振興協議会理事長、厚生労働省検査技師試験委員会委員長、厚生労働省先進医療専門家会議構成員、厚生労働省標準的な健診・保健指導のあり方に関する検討会構成員、厚生労働省 DPC 研究班分担研究者、厚生労働省顧問医、中医協専門組織委員会委員、中医協医療技術評価分科会構成員、東京都衛生検査所精度管理専門委員会委員長、文部科学省学術審議会専門委員(科学研究費分科会)、日本医師会疑義解釈委員会委員、日本医師会外部精度管理委員会委員、日本衛生検査所協会精度管理委員会委員長
この間は、国内外の臨床検査関連学会にほとんど全て出席した。特に国際学会にも参加し、多い時には一年に数回の海外出張があった。
このため私は多忙を極め、毎日時間毎の予定表を作って貰い、ただその通りに行動する日が続いた。一生の中で最も忙しい時期を過ごした。
学会や臨床検査団体で、特に印象に残っているのは以下の2 つの団体と外来の診療前検査の立ち上げに積極的に拘わった事である。
日本検査血液学会の創設
1990 年当時は血液学に関する学会は日本血液学会と日本臨床血液学会が主であり、この中で血液検査の学問である検査血液学は日の目を見ずに経過をしていた。ただ、日本臨床病理学会の中に臨床血液専門部会(以下血液部会)があり、ここで僅かながら検査血液学に興味のある先生方が集まり、検査血液に関する講演会を毎年開催していた。しかし、1992年には、国際検査血液学会が設立され、検査血液学が世界的にも認められてきた。国際的に検査血液学が発展するのを目のあたりにして、やはり日本にもこのような学会が必要であるとの思いが心の中に生じてきた。
その後、この学会の発足のため、血液が専門の有志医の先生方や全国の血液検査技師の方と懸命に話合った。また、関連企業の方にも個別に丁寧に対面でお願いし、賛助会員として資金を提供して貰った。1998年 12月24日のクリスマスイブの日に、この学会発足の検討会が開催され、臨床病理学会の血液部会の幹事と日本臨床衛生検査技師会の幹部が会合した。この席で医師と技師とで協力して、実学を中心とした検査血液学会を設立する方針が決定し、最終的に、2000年3月25日に日本検査血液学会が創設され、私が初代理事長に選出された。
本学会は検査室の実際の業務に役立つ組織として発展し、今は臨床検査でも特に隆盛を極めている(会員数:創設時約1,000名が現在は約4,000名)。これを見るにつけ創設当時の苦労が懐かしく感じられると同時にあの時どこかでひるんでいたら今の検査血液学会はなかったかもしれないと思っている。今後も本学会が初心を忘れず、医師、技師、企業の方々が共同で血液検査に有用な研究活動を、地味でも良いから確実に発展させて頂きたいと心から念じている。
臨床検査振興協議会の創設
2000 年当時私は診療報酬を決めている厚労省保険局医療課の官僚と接点があり、その中で診療報酬を決める仕組みなどを学んだ。1990年からのデータによれば検体検査の実施料は診療報酬改定毎に低下し、約40%と大きく下落を示していた。そこで分かったのは、検査専門医を含め検査関連の人達の検査の診療報酬への無関心というか、効率的な要望が不足している事であった。これを解決するためには、検査業界が産学共同で国にアプローチする必要があると感じていた。
私はたまたま臨薬協の 3 人の方にゴルフ場でこの話を持ち出し、臨薬協も含めて検査業界はこれを何とか打破するべく、具体的に策を練らないといけないと力説し、3 人からは賛同の意見を貰った。そして、「明日の臨床検査を考える有志の会」を作り、これが診療報酬改善への基盤となった。
2004年に日本臨床検査医学会の会長を拝命した関係で、ある日、厚労省の保険局医療課の課長補佐の方から「厚労省への診療報酬に関する要望は、今の検査業界がやっている書類だけの申請では全くインパクトに欠ける。外科学会のようにface to faceでの話合いをしないと何が問題か十分把握できない。また、臨床検査はいろいろな組織があり、個別にバラバラの要望を出してくるので、学会だけではなく業界全体で統一した要望をして欲しい」と大変貴重な意見を貰った。
そこでこの年には、さらにこの会に日衛協、臨床検査専門医会などに加入をお願いし、2005年には、業界全体で厚労省へ診療報酬改定を要望する臨床検査振興協議会が創設された。私は言い出しっぺと言う事で、この協議会の初代理事長に選出された。
臨床検査振興協議会では、厚労省と鋭意対面での折衝をし、検体検査実施料の適正化を行った。そして2006年に、1990年に比し約60%も下降していた検体検査実施料の保険点数は、臨床検査振興協議会の設立以来、現在まで下げ止まっている。ここ10数年不況の中で、薬価を初め多くの項目の保険点数が下げられている中で、検体検査実施料は現状維持が続いているのは大変良かったと思っている。下降線があのまま続いていたら、検査業界はどうなっていたかと思う。先進国に比しまだまだ検査の点数は低いので、今後さらに努力する必要があると言う意見はあるが、この下げ止まりは全臨床検査業界に大変大きな福音をもたらしている。
外来迅速検体検査の保険収載
元々私は血液内科医だったので、以前から外来で採血し、当日の血液検査結果で患者診療ができないのかと考えていた。2000年頃、慶応病院の検査部で患者の診察前検査を施行する事を決めた。検査部の人と話し合い「診療前検査」と称して、約80の検査項目を 1 時間以内に外来に報告するシステムを作った。その後本検査は大人気で増え続け4年間で慶応病院の総外来検査数の約半分が診療前検査になった。しかし、問題は診療前検査を施行しても、当時の保険制度では経済的に適正な評価を受けていない事だった。
2004年に日本臨床検査医学会の会長に選出されたので、学会としてやるべき事の一つに診療前検査の国での評価を得る事を考えた。またその頃、私は厚労省の保険医療専門審査員、先進医療専門家会議構成員、医療技術評価分科会委員などを拝命し、保険局医療課の官僚と接点が多かったので、保険について交渉し易い立場にあった。そこで、日本臨床検査医学会の保険点数委員会の委員長に帝京大学の宮澤教授になって頂き、まさに二人三脚で厚労省に診療前検査の保険収載について要望をした。診療前検査の普及は経済的な利点もあるが、本来疾患の早期診断と早期治療が可能となるので、宮澤先生も私も鋭意交渉をした。
そして 2005年4月に、学会から内保連へ最重点項目として本件を会長名で要望した。その要望書のコピーが手元にあるが、技術名は診療前検査加算、対象は外来の主要検査として、1時間以内に報告するとある。特筆すべきは予想される医療費への影響は 86 億円減との記載がある。これは保険点数委員の故米山彰子先生の素晴らしい発案によった。そしてこの案件は翌2006年度の診療報酬改定で「外来迅速検体検査加算」と言う名称で新たに保険収載された。病院に来たその日に採血などをして、検査結果が分かり診療するシステムは患者さんの日常診療に大きな貢献をしたと思っている。
お わ り に
このようにして、私は2005年3月に10年務めた医学部教授を定年退職した。
母校の創始者の福沢諭吉先生は「実なき学問は先ず次にし、専ら勤むべきは人間普通日用に近き実学なり」とその著書の学問のすすめで述べているが、まさにそのような臨床検査専門医としての日々を過ごした。
やってきた事で何が有用かは分からないが、とにかく専門医としては臨床検査の価値を少しでも上げると信じた事を懸命にやった積もりでいる。
臨床検査の価値を上げるべきであると説くのも大切であるが、自分でやってみるのも一つの生き方だと思う。是非トライアンドエラーで結構なので、若い先生方はチャレンジして頂ければと思っている。
JACLaP NEWS 147号 2024年3月掲載
- 投稿者: wp-bright
- 臨床検査医学への提言