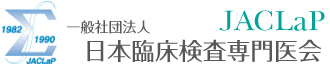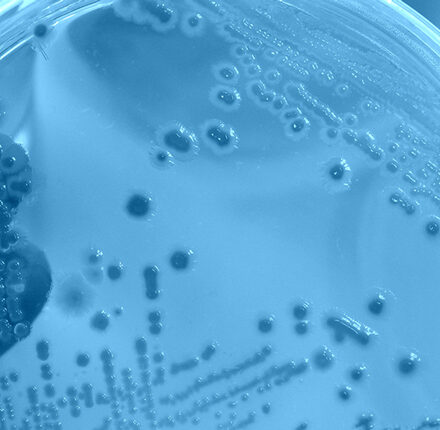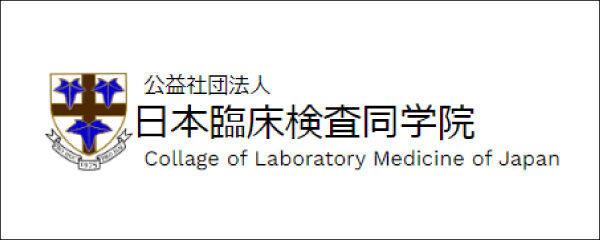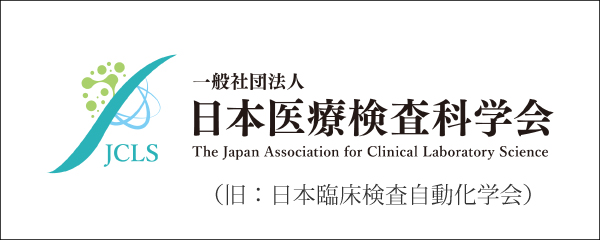沿 革
歩みと活動

日本臨床検査専門医会の歩みと活動
Ⅰ. 日本臨床検査専門医会の発足と経緯
1)臨床病理医の集い
東京都内の私立大学医学部4校(順天堂大学、日本大学、昭和大学、日本医科大学)の臨床病理学教室(現在の「臨床検査医学」は当時「臨床病理学」と呼ばれていた)に在籍中の若手教室員が自発的に集まって始めた勉強会「臨床病理医の集い」の第1回は、1977年に順天堂大学で開催された。目的はそれぞれの教室が得意とする分野を担当し、他大学で不足している臨床病理学分野の教育を補填しあうものであった。順天堂大学での第1回は「臨床微生物」、第2回は日本大学が担当して「免疫・血清検査」、第3回は昭和大学が担当して「臨床化学」に関する勉強会を行った。勉強会は年に1回の割合で開催された。その後、自治医科大学、北里大学、東京医科大学で臨床病理学を学ぶ教室員にも呼びかけ、勉強会への参加者は増加していった。この活動が日本臨床検査専門医会の発足に繋がっていくことになった。
2)臨床検査医会の発足
1979年に日本臨床病理学会(現在の日本臨床検査医学会)の認定医制度が開始された。これを機会に臨床検査ギルド集団の会の設立の機運が高まった。
1982年10月21日、第29回日本臨床病理学会総会(岐阜グランドホテル)にて「臨床病理医の集い」は、「臨床検査談話会」と名称を変えて第1回の会合を開催し、臨床検査医の職能団体としての会が立ち上がった。同年11月に代表幹事から日本臨床病理学会に文書で「臨床検査談話会」の名称を「臨床検査医会」とする旨を要望したが、日本臨床病理学会幹事会では議論はなされなかった。そこで1983年5月に村井哲夫先生を代表とし、正式に「臨床検査医会」を発足した。故にこの時点が日本臨床検査専門医会の発足時期となる。
3)臨床検査専門医制度の発足、そして新専門医制度のスタート
1951年、日本臨床病理学会の前身である「臨床病理懇談会」の第1回会議で「臨床検査を専門職とする臨床病理専門医が必要である」との話し合いがなされた。この時に初めて専門職としての臨床検査医の概念が専門家の間で浮上したとされる。その後、「臨床病理懇談会」は「臨床病理学会」と改称されたが、この間に専門医制度の具体案の検討が行われ、1955年の第2回日本臨床病理学会総会で「臨床病理専門医」の名称が正式に議題にあがった。そして臨床病理専門医制度の創設についての趣意書(臨床病理 3:342~344, 1955)が作成され学会総会の承認を得た。しかしながら臨床病理専門医制度を具体化するには研修施設の整備や研修指導者の十分な配備、卒後教育体制の整備などを行う必要があり、残念ながら当時はこれらの整備に対する対応は非常に遅々として進まなかった。
1966年頃から学生運動が盛んになり、医学部改革運動の中で卒後教育の在り方が論じられるようになった。この中で専門医制度についても検討される状況となった。これを機に日本臨床病理学会でも再び専門医制度案の推進を図ることになった。臨床病理医の研修過程の中で病理形態学の修練が必要とされ、また病理では認定病理医を作るべきとの意見があり、これらについて日本病理学会との整合性を図る作業が必要となった。専門医の名称を「認定臨床病理医」とすると「認定病理医」と紛らわしいとの意見があり、1969年頃から約10年間にわたり日本臨床病理学会と日本病理学会との折衝が行われた。紆余曲折の議論の結果、1979年に日本臨床病理学会の認定医制度は発効され、名称は「認定臨床検査医」と決まった。この年、学会の資格認定委員会で慎重な審議を経た後、過渡的措置として相当の実績と経験を有する日本臨床病理学会所属の医師が「認定臨床検査医」に認定され、わが国で初めて「認定臨床検査医」が産声をあげた。過渡的措置は5年間で終了したが、その数は合計219名であった。
1984年に日本臨床病理学会による「認定臨床検査医」の第1回認定試験が東京医科大学で実施され、臨床検査医の試験による選抜が始まった。その後、本試験が毎年実施されているのは承知のとおりであるが、2021年からは日本専門医機構による認定試験が始まった。
2014年5月に発足した日本専門医機構は、これまで各学会が独自に認定し、運用してきた専門医制度を共通のルールに基づいて運用することにした。2015年度から2019年度までは移行期間として学会認定の専門医を更新時に日本専門医機構が認定する専門医へ資格更新を行い、2020年に新制度に移行した。2021年8月に日本専門医機構による第1回の認定試験が行われ、3名の日本専門医機構認定の臨床検査専門医が誕生した。
4)日本臨床検査医会から日本臨床検査専門医会へ、そして任意団体から一般社団法人へ
本会は総会や講演会を日本臨床病理学会総会中に開催し、それが定着していった。1990年に本会から日本臨床病理学会へ両会の関係を明確化するよう申し入れ、日本臨床病理学会がそれを認め、両会が相互に協力することが承認された。同年4月に本会の名称は「日本臨床検査医会」に変更され、幅広く全国から幹事を選出し、新会長に河合忠先生が就任した。その後、本会は順調に発展し、「臨床検査医会」発足当初80名であった会員数は年々増加し、「日本臨床検査医会」への移行時には230名程となり、2022年8月31日現在の会員数は608名(賛助会員数は除く)である。
2000年に「日本臨床病理学会」が名称変更を行い、「日本臨床検査医学会」となった。その際に「日本臨床検査医会」の名称が「日本臨床検査医学会」と類似していることから名称変更の必要が生じ、2003年に本会は「日本臨床検査専門医会」に名称変更し、現在に至っている。
本会のマネジメントの中心である事務局は、庶務会計担当幹事の所属機関に設置されていたが、2004年11月に本会の事務所を御茶ノ水に設置し、専任職員が従事することになった。その後、事務所が手狭になったため2010年6月に事務所を秋葉原に移転した。
任意団体であった本会は、2020年に法人化WGを立ち上げ、2021年に法務局への登記手続きを行い、2022年1月1日から任意団体よりも社会的信用力がある一般社団法人になった。
Ⅱ. 主な活動
1)会 議
2021年までの任意団体では、総会、幹事会、常任幹事会、各種委員会が主な会議であったが、2022年からの一般社団法人では、社員総会、理事会、常任理事会、各種委員会が主な会議である。
2021年までの任意団体では、総会は毎年春季大会と日本臨床検査医学会学術集会にあわせて2回開催され、本会の重要課題を審議・決議していた。一般社団法人となった2022年からは6月までに開催される臨床検査専門医会年次大会(春季大会から年次大会に名称を変更した)での定時社員総会と日本臨床検査医学会学術集会時に開催される臨時社員総会の2回で本会の重要課題を審議・決議する。
2021年までの任意団体における幹事会は、会長が正会員の中から選任し、委嘱した幹事をもって構成されるが、日本臨床検査医学会の支部が置かれている地域を考慮して選考されるために「全国幹事会」と別称された。幹事の中から会長が委嘱する常任幹事は、会長、副会長および監事とともに常任幹事会を構成する。一般社団法人設立後の常任理事は、理事選挙により当選した理事が務め、理事長候補は理事の互選で選ばれる。理事長もしくは理事長候補は地域等を考慮して理事を8名まで指名することができる。なお、一般社団法人設立時のみ任意団体の常任幹事が常任理事に移行した。
2021年までの任意団体では、委員会は7つ(情報・出版、教育研修、資格審査・会則改定、保険点数、渉外、広報、ネットワーク運営)であったが、2022年からは委員会は6つ(情報・出版、教育研修、資格審査・規定改定、保険点数、渉外、広報・ネットワーク)となった。各委員長を2021年までは常任幹事および副会長が務めたが、2022年からは主に常任理事が務めることになり、各委員会は鋭意活動している。
他団体との連携活動にも積極的に参加しており、JCCLS、WASPaLM、内保連、臨床検査医学会、臨床検査専門医・管理医審議会には委員を、臨床検査振興協議会には役員ならびに委員を派遣している。
2)セミナー
(1)教育セミナー
1984年に臨床検査医の認定試験が開始されたのを機に、1985年から認定試験を念頭に置いた臨床検査医としての最低限必要なエッセンスを習得するための教育セミナーが開始された。臨床検査医学は非常に領域が広く、各分野の詳細について学ぶことが難しく、また認定試験では従来の学会認定専門医と同様に日本専門医機構の専門医においても筆記試験のみならず実技試験が厳格に行われるため、本セミナーは効率的に臨床検査の各分野の知識や技能を理解するために極めて有用である。
当初は主に東京の私立大学を中心に毎年3~4回のセミナーを開催(関西でも実施したことがある)し、臨床検査専門医の認定試験受験者向けのセミナーとして継続してきた。しかし、実習形式のセミナーは開催を担当できる施設が限定され、しかも担当施設の負担が大きいために継続を断念し、現在は講義形式の教育セミナーを年1回開催している。2020年からはCOVID-19の感染拡大により対面形式でのセミナーが実施できなくなり、WEBによるセミナーを開催している。
(2)臨床検査振興セミナー
本会の会員は、正会員と賛助会員からなるが、賛助会員は本会の趣旨に賛同する主に臨床検査関連の企業で構成されている。賛助会員からは日頃よりさまざまな支援、特に経済的支援をいただいており、賛助会員による支援は本会に不可欠なものである。
毎年7月に開催している臨床検査振興セミナーは、賛助会員への感謝の機会であり、臨床検査の学術的あるいは最新の情報を提供することと、賛助会員と臨床検査専門医との交流を目的としている。隔年の診療報酬改定に合わせて医療行政に関する情報を提供し、時には臨床検査のトピックスを講演のテーマにするなどして賛助会員から好評を得ている。賛助会員は「振興会員」と呼称されていたが、2008年度の会則改定で名称が変更され、それに伴い「振興会セミナー」も「臨床検査振興セミナー」へ名称が変更された。また、2008年は本会設立25周年の節目でもあったため、本会設立25周年記念式典とともに開催された。
30年以上続けてきた臨床検査振興セミナーは、COVID-19の感染拡大により2020年は開催中止、2021年以降はWEBによるセミナーとなり、賛助会員と臨床検査専門医との懇談の機会がなくなっている。
3) 生涯教育講演会
(1)GLMワークショップ
臨床検査専門医にとっては質の高い検査成績を臨床へフィードバックするための臨床検査室の管理運営が極めて重要である。この臨床検査専門医の業務をブラッシュアップする目的で、臨床検査専門医に重要な実践的課題についてGLM(Good Laboratory Management)ワークショップが行われている。当初は自治医科大学の研修センターで1泊2日のスケジュールで行われ、夜の酒席を囲みながらの意見交換も臨床検査室の管理運営の貴重な情報源となっていた。GLMワークショップは、2004年からは専門家による講義形式のGLM教育セミナーに形を変えたが、1993年から年に1回の割合で毎年開催されてきた。
(2)生涯教育講演会
2011年から本会の全会員を対象として「臨床検査専門医会 生涯教育講演会」の名称でリスクマネジメントと検査室管理に関する講演会を年1回春季大会にあわせて開催するようになった。この講演会は日本臨床検査医学会のリスクマネジメントに関する講演会の一つに認定されており、講演会参加により臨床検査専門医の受験や更新に必要なリスクマネジメントに関する履修単位を取得できるようになっていた。新専門医制度となった現在は、日本専門医機構の専門医の更新申請に必要な専門医共通講習(医療倫理、医療安全、感染対策など)や臨床検査領域講習の単位を取得できるようになっている。
4) 春季大会(年次大会)
1991年4月に京都にて大場康寛先生の主催で第1回春季大会が開催されて以来、毎年春季大会が開かれていたが、COVID-19の感染拡大により2020年の橋口照人大会長の第30回春季大会は開催延期となった。翌年(2021)5月には第31回春季大会が秋田にて植木重治先生の主催でハイブリッド開催される予定であったがCOVID-19の感染拡大により直前になってWEB開催のみに変更となった。2022年は一般社団法人となって初めてとなる第1回年次大会(春季大会から名称を変更した)が5月に鹿児島市にて橋口照人先生の主催でハイブリッド開催された。春季大会では臨床検査のマネジメントや臨床検査のあり方など臨床検査専門医にとって必要な情報に関する講演が企画され、議論されている。また、臨床検査医学に関連するトピックスについて臨床検査医学の各分野および他分野の専門家を講師として招き、相互の理解を深めるプログラムが実施されている。
5) 情報・出版
臨床検査専門医の情報交換ツールとして、情報・出版委員会が中心になって以下の出版物を発行している。
(1)JACLaP NEWS:1991年から会員の動向、委員会議事録、年間スケジュール、人事異動、最新の臨床検査関連ニュースおよび会員の声などを掲載して年間3回のペースで刊行している。また、新規に保険収載された検査のまとめも掲載されており、日常検査業務にも寄与している。2021年のNo.138から「臨床検査医学への提言」の連載を開始し、第1回は前会長の登勉先生、第2回は元会長の佐守友博先生、第3回は本田孝行先生、第4回は櫻林郁之介先生に執筆していただいた。
(2)JACLaP WIRE:より一層迅速に臨床検査関連情報を周知するための電子メール新聞である。1998年4月からメールアドレスを登録している会員へEメールで配信している。
(3)会誌「Laboratory and Clinical Practice」(通称:Lab CP):1983年から年に2回発刊されていた会誌であったが、2019年と2020年は年に1回の発刊となり、2021年と2022年は合併号となった。専門家による各検査領域の話題のレビュー、RCPC、New Technology、各種集会記録、大学医学部の臨床検査医学教育の紹介、本会春季大会の教育講演や日本臨床検査医学会学術集会での本会との共催シンポジウムなどが掲載されている。
(4)要 覧:会則や会員名簿などを掲載した「日本臨床検査専門医会要覧」を2010年までは2年に1回発刊していたが、その後は2015年と2018年に発刊した。会員相互の交流や会員消息を知る上で参考になるが、個人情報の取扱には十分留意している。
6)広報・ネットワーク委員会
広報・ネットワーク委員会は日本臨床検査医学会のワークライフバランス委員会と協力して臨床研修医が臨床検査に興味を持つような企画を立案し、実行している。例えばハンズオンセミナーや日本臨床検査医学会学術集会時のワークショップである。また、研修医が勉強のために読む機会が多い雑誌「レジデントノート」に「臨床検査医がコッソリ教える… 検査のTips!」を連載しており、2022年10月号で67回目となる。
7)保険点数
2年毎の診療報酬改定では、これまで多くの検査項目が削除され、減点されてきた。本会は日本臨床検査医学会の臨床検査点数委員会と協力して内保連ルートでの各種要望を行うとともに、独自のアンケート調査(免疫電気泳動に関する会員アンケート調査)も実施してきた。今後も会員の声を診療報酬改定に反映できるように様々な活動を展開していきたい。
8) 臨床検査振興協議会
臨床検査振興協議会は、国民、行政および医療機関などを対象に、広く臨床検査の重要性の理解を求め、その適正な活用を推進し、国民の健康に寄与することを目的として2005年に任意団体として設立されたが、2022年1月1日に本会が任意団体から一般社団法人になったのを契機に、2022年4月1日から一般社団法人となった。本会を含め臨床検査に関わる5つの団体(一般社団法人日本臨床検査医学会、一般社団法人日本臨床検査専門医会、一般社団法人日本臨床衛生検査技師会、一般社団法人日本臨床検査薬協会、一般社団法人日本衛生検査所協会)から構成され、国民および医療関係機関などへの広報活動や、社会保険診療報酬等医療関係制度における臨床検査の評価を向上させ適正な活用を促進するための行政などへの活動を行うために5つの委員会(診療報酬委員会(診療報酬改定小委員会、診療報酬制度小委員会)、医療政策委員会(在宅医療における臨床検査小委員会、遺伝子関連検査に関する小委員会、感染症対策に関する小委員会)、広報委員会、大規模災害対策委員会、将来ビジョン検討委員会)で活動しており、本会からも役員(副理事長:〆谷直人、理事:山田俊幸)および委員を派遣している。
臨床検査振興協議会は、広報活動の一環として11月11日を「臨床検査の日」と制定した。「11月11日は臨床検査の日」をキーワードに、一般向けや医療従事者向けイベントの開催、臨床検査キャラクターを活用した広報ツールの作成、一般・高校生向けのDVD作成などを通じ、臨床検査を正しく理解してもらうために各会員団体による広報活動を推進している。
9) 全国検査と健康展
本会は2013年度から「全国検査と健康展」を日本臨床衛生検査技師会と共同開催している。「全国検査と健康展」は臨床検査の日の11月11日に近い10~12月にかけて都道府県の臨床衛生検査技師会が企画し、一般向けのイベントを開催している。検査機器の見学と簡易な検査の体験や検査結果に関連する医療相談会、医療講演会など、それぞれ趣向を凝らした内容である。本会は主に臨床検査専門医による検査説明・相談会を担当し、依頼を受けた都道府県の会場へ臨床検査専門医を派遣している。出務先は臨床検査専門医の地元や比較的近距離の会場が多いが、可能な場合は遠隔地への出務を依頼している。これにより地元の臨床検査技師との交流だけでなく、普段では交流できないような地域の臨床検査技師や臨床検査専門医同士の交流・情報交換ができる。また、2016年度からは「全国検査と健康展」の参加証が発行されるようになり、専門医更新の単位取得もできるようになった。2019年までは20以上の会場へ延べ40人程の臨床検査専門医を派遣したが、COVID-19の感染拡大により2020年以降は小規模な開催となっている。2022年は本会から5県(宮城、秋田、福島、京都、大分)へ臨床検査専門医6名を派遣した。
10) 専門医会ネットワーク(Q&Aシステム)
臨床検査に携わる医師の抱える課題を解決すべくQ&Aシステムを発展させた新しい臨床検査専門医会ネットワークシステムを構築し、臨床検査に携わる医師の資質の向上、育成、相互の発展を図ることを目標に、2014年に専門分野別ネットワーク構築WGを立ち上げ、2016年からはネットワーク運営委員会として活動してきた。その後、2022年にネットワーク運営委員会は広報委員会と合体した。
11)その他(臨床検査専門医の抱える課題)
大学医学部における臨床検査医学教育の実態は、決して満足すべきレベルにない。その理由の一つは教授の退任に際して臨床検査医学講座が他の講座に改組され、あるいは講座でなく中央検査部のみに再編される例が増えてきているからである。登前会長は2017年6月にアンケート調査を実施し、集計結果を関係者が方策を考えるデータとして公開した(JACLaP NEWS 134:4~5, 2019)。学問の領域として臨床検査医学は分野が多岐にわたっており、全分野を一つの教育機関でまかなうことが難しいためか、日本専門医機構の19の基本診療領域の一つに臨床検査専門医があるにもかかわらず、臨床検査医学の講座のない医学部があることがアンケート結果より明らかになった。
この他にも臨床検査専門医であることが検体検査管理加算(Ⅳ)を請求できる医師の必須条件となっていないことや、臨床検査専門医の医療における認知度が臨床検査技師の認知度より低いことが課題として挙げられる。
近年、嬉しいことに本会は若手の会員が増えている。そこで本会の運営にもっと若い力と若い知恵を導入し、臨床検査専門医の抱える課題の解決に取り組むようにしたい。