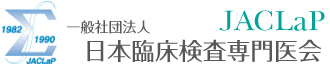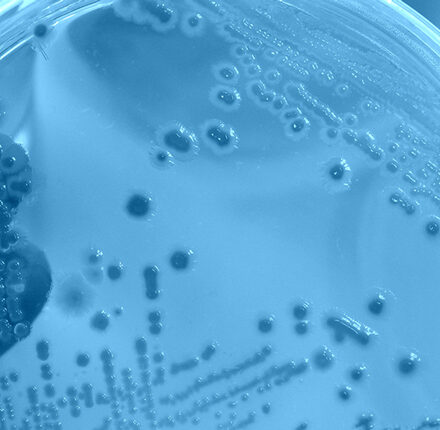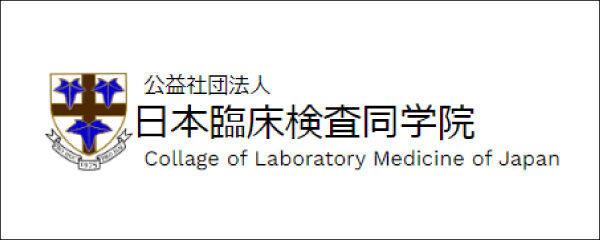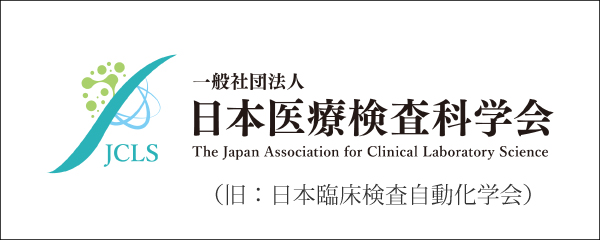臨床検査医学への提言 第八回 高木 康 先生

臨床検査に育てられ、仲間と奮闘した半世紀
昭和大学名誉教授
高木 康
臨床病理学(臨床検査医学)に足を踏み入れて半世紀が過ぎようとしています。長いようで短い時間の流れのなかで、「我が臨床病理(臨床検査)の足跡」を振り返る機会を与えて下さり、感謝します。こんな臨床検査専門医もいるのだと感じていただければ嬉しい限りで、休憩時間にお読みください。前6人のようなアカデミアではなく、実学としての臨床検査医学の過去の栄光と現在の立ち位置も加えて、筆を執ることにします。
最初は腰掛のつもり
1976(昭和51)年昭和大学医学部を卒業して、はてどの道に進もうかと迷っていた。臨床診療科に行く道も考えたが、人生いたるところにキーパーソンがいるようで、バレー部の先輩に、「今からは臨床検査が診療では重要になる。臨床に行くにしても臨床検査を学んでからでも遅くはない。大学院生になって研究するのも良い」との囁きが一生を決めてしまった。当時は、臨床検査は黎明期であり、その重要性が認識され始めた時期であった。確かに、患者診療を行うのに臨床検査を知っておくことは重要なことであり、しかも臨床病理学教室を主宰していたのは、真摯で学者然としているがどこかヒトを引き付ける魅力のある石井暢教授であった。総勢7名の小さな教室であったが、4人目の大学院生として入局した。居心地は良く、しかも臨床検査部を統括しており、お山の大将でもいられたので、楽しい大学院生活を送ることができた。
石井教授は、「臨床病理学教室は研究と教育は他の診療科と同じですが、診療は臨床検査であり、精確な臨床検査成績を医師や患者に届けるのが日常診療です」とのお考えから患者診療は行わずに、臨床検査に特化した教室運営を行っていた。
臨床検査に精通するために、大学院生を含む入局者は、血液検査室、血清検査室、生化学検査室、細菌検査室を約3ヵ月かけてローテーションし、それぞれの検査室の日常業務を身に着け、検査技師と同等の技能を修得することを義務付けられた。そして、自分に合った検査室の担当となるシステムであった。筆者はまず血清検査室をローテートした。血清検査室は筆者を臨床病理に誘導した先輩が担当しており、未熟な医師を温かく処遇してくれる古き良き時代の雰囲気の検査室であった。梅毒血清検査、CRP(当時は毛細管法で実施)、血液型検査・交差適合試験等の血清検査を実体験し、血液型試験・交差適合試験は技師並みの技量であった(と考えていた)。血液検査では、ローテートする前に上級医からディスカッション顕微鏡で塗抹標本のイロハを伝授され、検査室では検査技師に交じって日常検体標本を判読し、分からない細胞は上級技師に教えを乞うた。また、骨髄塗抹検査のコメントは新谷和夫博士(関東逓信病院検査科)が行っていたが、その下書きを担当し、年間200件超の骨髄検査標本を判読し、標本の内容を記載し、新谷先生が塗抹標本からの診断を記載した。新谷先生からはその時々に血液検査の最新の知見・細かな判別点などについてお教えいただき、それ以降は血液検査室の担当となった。
生化学検査は石井教授の専門分野であったので、新しい検査を新しい測定法・装置で測定しており、当時は画期的であったLKB 8600 による初速度測定法(レート法)を紫外部で測定し、反応曲線に罫線を引いて340nmでの吸光度の減少・増加を計算して、酵素活性値を算出する方法を検査技師が行っていた。生化学検査室には毎日500件近くの検体が集まり、当初は検査技師が 1 つずつの検査を受け持ち、用手法で検査していた。入局してすぐに自動分析装置(日立708)が導入され、新規項目の検査を実施できる体制を築くことができた。
生化学検査室では試薬・装置の検討用に必要な残余血の収集法を学んだ。当時は残余血の試薬・装置検討の利用に対するコンプライアンスはそれほど厳しくなく、残余血は比較的容易に準備できたが、検査済みで検討に利用可能な検体の抽出法について主任から厳しく仕込まれた。「あくまでも検査が優先ですから」と言われ、それでもできるだけ新鮮な残余血の収集法を伝授された。石井教室には新規の検査試薬・装置の基本的・臨床的検討の依頼が多く、1年に5~6個の検討を行った。この試薬・装置の検討結果を論文としてまとめる作業は後日の博士論文の作成時に大いに役立った。原稿用紙にダブルスペースで書いた論文を石井教授に提出すると翌日か翌々日には修正点が明示された原稿が返却されたので、追加検討が必要な場合はこれも追加して修正して提出した。数回の原稿の往復で全ての文章を暗記できるくらいになり、研究論文、石井先生の文章の書き方を知らない間に修得できたように思う。石井先生からは、「受け取った原稿は一両日中には修正箇所を明確にして返却しなさい。長い時間、手元に置いてはいけません」と厳しく指導された。その後は手元に届いた論文はご指導のように対応したつもりであったが、長い間手元に留め置いた原稿も少なくなく、赤面の思いであった。
臨床検査の仲間・同期生に恵まれた
昭和40~50年代の臨床病理学会は東京の3私立大学(順天堂大学、日本大学、昭和大学)を中心に回っていると言っても過言ではなかった。昭和36年に小酒井望博士により順天堂大学、38年に土屋俊夫博士により日本大学、そして39年に石井暢博士により昭和大学医学部に臨床病理学教室が開講された。これら3教室には主宰者の人徳と学問的業績を慕って多くの門下生が入局した。順天堂大学には只野寿太郎、森三樹雄、猪狩淳、伊藤機一、水口國雄、日本大学には櫻林郁之介、中野栄二、桑島実、熊坂一成、土屋逹行、村上純子、そして、昭和大学には五味邦英、細谷純一郎、千住紀等が在籍して、臨床病理(臨床検査)の研鑽を重ね、後日学会の中心人物として活躍した。その他にも日本医大の皆川彰、東京医大の池松正次郎、佐守友博、福武勝幸、慈恵医大の町田勝彦などとは「同じ釜の飯を食った」仲間のように付き合い、臨床病理学を切磋琢磨できたのは非常に光栄であった。
これらのなかで日大の熊坂君(熊さん)、土屋君(逹ちゃん)とは40年近くの親密な付き合いとなり、実学として臨床検査をともに歩んだ。両君は血液検査でのFAB分類での我が国の先駆者として、その導入と啓発に大いに貢献した。両君はオモテ(個性的)とウラ(ステレオタイプ)の関係のように、お互いがフォローしあって日大の、我が国の臨床検査を牽引してきたと言えよう。今では多くの検査医学教室に設置されている臨床検査に対する「On Call Conference、検査に関する質問とその対応」の導入、R-CPCの導入と臨床検査学の臨床実習の基本システムを構築、医学教育カリキュラム設定手法を用いた臨床検査室の改善・改良システム(GLMワークショップ)の導入等にリーダーシップを発揮し、実学である臨床検査へ大いに貢献してきたと考えるのは筆者だけであろうか?
認定医制度による臨床検査医の最初の認定医試験が行われたのは 1984(昭和59)年である。両君はこの認定医試験の第1回の受験生であり、見事に合格した〔筆者は過渡的処置の適応を受け(石井教授からの推薦もあり)、研修登録して認定となったが、両君はことあるごとに認定試験の合格者であることを誇っていた〕。臨床検査は広範囲であり、全ての領域に精通することはやさしい事ではない。このため、認定医として最低必要な事項を認定医試験と関連付けて1985(昭和60)年に始まったのが「教育セミナー」である。日大で「輸血と血液型検査」、順天堂大学で「微生物検査」、昭和大学で「生化学検査とサンプリング」を担当して、毎年開催した。臨床検査専門医試験は数少ない実習をベースにした試験であり、このことは専門医機構でも高く評価されている。「教育セミナー」を実技試験の形式で行うのにその準備は並大抵ではない。当時は一人でも多くの検査専門医を育成する、仲間を増やすという熱き血潮で頑張った。検体管理加算に関連して病理医が臨床検査医認定試験を受験した1995~2000 年での「教育セミナー」では「病理学会ではこのような後輩思いのセミナーは開催されていません。臨床病理学会が羨ましいです」との言葉をよく耳にした。この時期には毎年50名近い受験生(1997年43名、98年41名、99年55名、2000年51名)であり、このまま継続すれば念願の1,000人となることを夢見ていた(厚労省等は医療施設に常勤する専門医を設置するには最低1,000名が一応の目安と考えていた)。
検査の標準化と検査値の互換性
臨床検査の標準化、検査値の互換性の保証は臨床検査に籍を置く医師・関係者に課せられた命題である。「日本専門医機構」で、専門医の再構築が行われた2000年前後に、「臨床検査医学とは何か。一般人にも分かるような定義を考えてください」との質問に対する専門医機構とのヒアリングで機構委員から出た言葉は今でも忘れることができない。「診療科での重要な臨床検査の項目の選抜は各学会が行いますので、臨床検査医学会では、精確な検査成績を診療科に返却することが業務ではいかがですか。新しい検査項目は診療科と協働して開発しますが、検査法は臨床検査医学会で開発・改良をお願いします。」とのコメントであった。当時は東京医大をはじめとする少なからぬ臨床検査医学講座で日常診療を行っていたが、臨床検査医学に求められているのは、検査の標準化と精確な検査値の患者・臨床への返却であることをダイレクトに言われ、驚愕するとともに周囲・国民はこのことこそが臨床検査医学と考えていることを改めて問いただされた。
そして、『臨床検査専門医は臨床検査(血液や尿などを対象とする検体検査と心電図などの人体・生理機能検査)に関する専門的医学知識と技能を有し、臨床検査が安全かつ適切に実施できるよう管理し、医療上有用な検査所見を医師・患者に提供する医師です。新たな臨床検査の研究および開発を行うと共に、臨床検査医学の教育に従事する医師です。』を臨床検査医学会として専門医機構に提出した。現在の HP にも『臨床検査医とは、検査室を管理するとともに、検査にかかわる診断業務を行う医師です。検査技師の方々と協力して、検査を適切に実施し、正確で精密なデータを返却できるよう努力しています。日常診療では、「正確なデータが返ってくるのが当たり前」と思われているかもしれませんが、それは検査部医師・技師の日々の努力のたまものなのです』としており、「精確な検査データ・互換性のあるデータ」は日常診療上極めて重要であり、この保証をするのが検査専門医の重要な業務の1つであることを現在に生きる検査専門医は再考してほしい。
我が国には、日本医師会、日本臨床検査技師会、日本衛生検査所協会、全国労働衛生団体連合会、日本人間ドック学会、各自治体主催の精度管理調査委員会がある。これら委員会のどこかに籍を置き、国・地域の臨床検査の精度管理、検査施設での標準化・互換性の確保の中心的や役割を果たしてほしい。
今後の臨床検査医
-診療支援に積極的に関与する臨床検査医-
臨床検査医の業務の1つに「診断支援システム」がある。多くの臨床検査医はシステムの違いはあるが少なからずこの領域で活躍している。2023年6月に開催された日本臨床検査専門医会第2回年次集会での米川修博士が電子カルテの導入により臨床検査医(検査室)が行う診療支援の具体例を発表した。
『「診療支援システム」は、担当医の依頼による検査の結果が検査室で定めた異常値に 1 項目でも該当すれば、その日依頼された全検査項目がプリントアウトされる仕組みになっています。それを臨床検査科医師と検査技師が病態解析し、必要に応じ追加検査を実施、その結果を踏まえて担当医へ電話連絡したり、コメントをカルテへ入力したりします。検査データに異常があれば、臨床検査科医師・担当医・検査技師の三者が確認し、迅速的確に対応します。「診断支援システム」は、検査データの確実な確認に加え、検査データそのものを評価することで患者さん自身に自覚のない異常を早期に発見できるメリットもあり、担当医師の診療の補助と「医療の質」の向上につながっています。』
従来から臨床検査医が個人的に特定の診療科で臨床検査成績に関わってきた。しかし、現在では診療システムとして臨床検査医が関与することが期待されている。チーム医療が叫ばれて久しい。また医師の働き方改革が推進されている現在、検査室の医師・技師が患者の臨床検査データに対して責任を持つ時代になった。熊さんの「On Call Conference」の受け身での検査相談の時代から臨床検査データからの診療への積極的参加が令和時代に求められている。電子カルテ・ITの診療現場での使用拡大により、臨床検査医(臨床検査技師)が診断支援の現場に登場することが可能な時代となったのである。ただし、これら底流には「精確な検査データを患者診療に返却する精度管理の一層の充実・向上」が必要不可欠であり、その総責任者も臨床検査医であることを忘れないでほしい。
人生はヒトとの出会い、素晴らしい出会いでした
-尊敬できる師、相談できる同期生-
臨床検査の領域に足を踏み入れてはや半世紀が過ぎようとしています。昨今はヒトとの出会い・邂逅の不思議さを実感し、新しい診療支援の現場である臨床検査に身を置いた半世紀の恵まれた環境に感謝しています。後輩の皆さま、諸君の未来を輝けるものにするには、現実を直視し、ヒトとの出会いを大切にし、臨床検査を「業」とする仲間を増やしてください。仲間から情報を得、仲間と一緒に考え・行動することで、臨床検査医学は第二の黎明期を迎えるものと確信しています。ご健闘をお祈りしています。
JACLaP NEWS 146号 2023年10月掲載
- 投稿者: wp-bright
- 臨床検査医学への提言