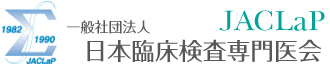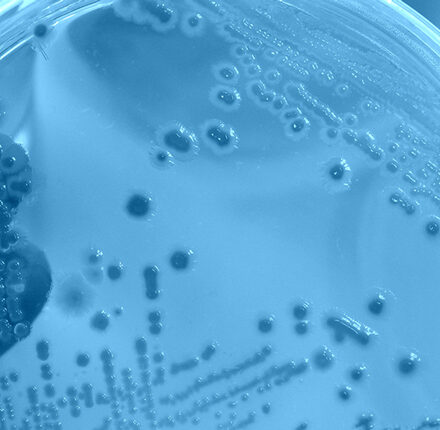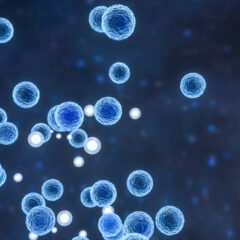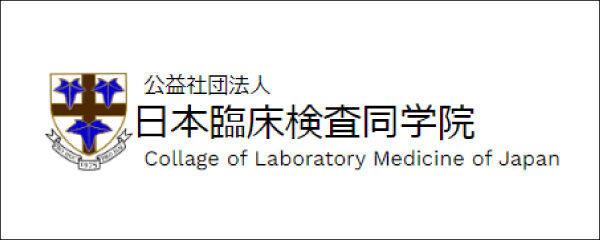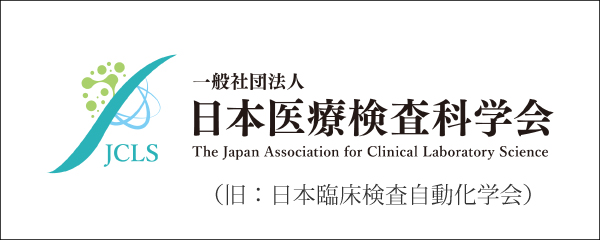臨床検査医学への提言 第七回 賀来 満夫 先生

東北大学 名誉教授
賀来 満夫
今回、九州大学名誉教授 濱崎 直孝 先生より御推薦いただき、日本臨床検査専門医会会報(JACLaP NEWS)に寄稿する機会をいただき大変感謝している。
本稿では、私と臨床検査医学との関わりについて紹介させていただくとともに、東日本大震災をはじめとする自然災害そして感染症パンデミックにおける臨床検査、臨床検査医学の重要性、最後にワンヘルスコンセプトとそのコントロールの重要性について、私見を述べさせていただくこととする。
I.私と臨床検査医学との関わり
私は1981年(昭和56年)に長崎大学医学部を卒業し、大学病院で1年間臨床研修を行った後、故臼井敏明教授が第2代教授として主宰されていた長崎大学医学部臨床検査医学講座(初代教授は故糸賀 敬先生、第三代教授は故上平憲先生、第四代現教授は柳原克紀先生)の大学院に入学し、当時、教室の講師であられた故山口恵三先生(後に東邦大学医学部微生物・感染症学講座教授に就任)のもとで、臨床検査医学ならびに臨床微生物学の研究に従事し、レジオネラに関する研究テーマで学位を取得した。
当時の臨床検査医学教室の大学院には、大阪大学医学部感染制御学教室前教授である朝野和典先生、東邦大学医学部微生物・感染症学教室教授である舘田一博先生、石井良和先生、国際医療福祉大学医学部感染症学教室教授である松本哲哉先生、東北大学医学部臨床微生物解析治療学寄附講座教授(現栗原市立栗原中央病院 感染制御センター長)の平潟洋一先生などが在籍し、細菌の薬剤耐性メカニズムや病原性解析などに関する様々な研究テーマに精力的に取り組み、多くの研究業
績が生み出された。
その後、私は1989年(平成元年)に自治医科大学呼吸器内科学教室に在籍し、当時、自治医科大学臨床病理学教室教授であられた河合 忠先生に臨床検査医学全般について指導していただき、1990年(平成2年)には長崎大学医学部附属病院検査部の講師に着任し、臨床検査医学、臨床微生物学の研究・教育に取り組むとともに、当時はまだ珍しかった感染管理・感染制御の分野に関する研究に取り組み始めた。
1995年(平成7年)7月から聖マリアンナ医科大学微生物学教室に在籍した後、1999年(平成11年)3月に東北大学大学院医学系研究科分子診断学分野(後に感染制御・検査診断学分野、さらに総合感染症学分野に改名)教授に就任し、併せて附属病院検査部長として、研究・教育・診療の任を担うこととなった。教室の臨床検査医学分野の研究においては、臨床微生物学の研究を中心に研究が進み、教授在任中に18名の教授を輩出した。さらに、検査部では夜間・休日検査室では2003年(平成15年)に大学病院検査部単独としては国内で第一号となるISO9001認証を取得し、臨床検査の国際的な標準化を推進する「臨床検査医学におけるトレーサビリティ合同委員会(JCTLM)」により、全世界で100ヵ所、日本国内では6ヵ所しかないレファレンスラボとして登録され、さらに2011年(平成23年)4月には ISO15189認定(臨床検査室―質と適合能力に対する特定要求事項)を取得し、現在に至っている。
その後、2019年(令和元年)に東北大学を退官したが、医学部卒業後、すぐに臨床検査医学に触れ、以後、現在に至るまで、実臨床における臨床検査の重要性、そして、様々な臨床検査の精度を高め、データの解析評価や新たな診断法の開発研究そして臨床病態を解析評価する、臨床検査医学という学問分野の重要性を深く認識していたが、その認識は東日本大震災の発生、新型コロナウイルス感染症のパンデミックの出現によって確信となっていった。
II.自然災害そしてパンデミックにおける
臨床検査・臨床検査医学の重要性
2011年(平成24年)3月11日の地震(マグニチュード9.0)の発生、そして、その後、東北の湾岸地域を襲った巨大津波は、我が国の歴史上かってなかった規模の未曾有の災害をもたらした。特に被害が大きかった東北の湾岸地域では、環境衛生の悪化に加え、電気や水、ガスなどのライフラインが完全に断たれ、地域の一次医療を支えていた地域のクリニックや診療所、二次医療を担当していた拠点病院も甚大な被害を受けるなど、まさに地域医療そのものが崩壊した状態となり、医療施設はもちろんのこと、避難所での感染症の発生が懸念される状況に陥ることとなった。
発災後、初期には環境からヒトへ伝播する環境微生物が原因となる破傷風やレジオネラ感染症などの発生がみられたことに加え、多数の人々が狭い空間のなかで生活を余儀なくされていた避難所などでは、インフルエンザやノロウイルス感染症など、高率にヒト―ヒト伝播する微生物が原因となった感染症が発生した。さらに、避難所では水や電気などのライフラインが途絶していたため、寒さや栄養不足などからの基礎疾患の悪化に伴う続発性の感染症や不十分な口腔衛生・誤嚥などが原因となった二次性の細菌性肺炎症例などが増加し、拠点病院に搬送される患者が増加した。
東北大学病院においても検査部のあった建物が被害を受け、一部の血液検査などを除き、生化学検査、血清検査、免疫学検査、微生物学検査など、ほとんどの臨床検査が行えなくなるという事態に陥った。様々な疾患に罹患している入院・外来患者の診断や病態解析などができなくなる事態となり、東北大学病院のすべての診療科の誰もが、あらためて臨床検査の重要性を再認識することとなった。
巨大地震という自然災害の発生により、臨床検査の重要性が強く認識されたことで、検査部の再建が東北大学病院の最優先課題となり、2013年(平成25年)3月には、新たな検査棟への検査部の移転、機器更新などが行われ、我が国初となる「震災対応総合臨床検査システム」が構築された。これらの新たなシステムに基づいた検査は、認定臨床微生物検査技師、認定血液検査技師、認定一般検査技師などの資格認定を取得した臨床検査技師を中心に検査部医師や各診療科の医師と連携し、高度先進医療施設に相応しい質の高い検査が提供されることとなった。
また、今も大きな問題となっている新型コロナウイルス感染症は、2019年(令和元年)12月31日に中国武漢で発生した原因不明の肺炎として報告されて以来、全世界で感染が拡大し、2023年(令和5年)3月1日の時点で、世界で7億5,830万人以上の感染者数、685 万人を超える死者数、我が国でも3月4日の時点で、3,325万人以上の感染者数、7.2万人を超える死者数が報告される状況となっている。21世紀になって人類が経験した重篤化するコロナウイルス感染症としては2002年(平成14年)の SARS、2012年(平成24年)の MERS、そして今回の新型コロナウイルス感染症が知られているが、今回の新型コロナウイルス感染症が世界的流行:パンデミックとなり、これほどの広がりと被害が起こることは、人類にとって、1918年(大正7年)に発生したスペイン風邪に匹敵するほどの出来事であり、まさに 100年に一度の感染症:メガクライシス(巨大な危機)といっても過言ではない。
感染症対応のポイントは、迅速かつ確実な診断に基づき的確な治療を行うこと、そして感染予防を徹底し、感染の蔓延を防ぐことにあるが、今回の新型コロナウイルス感染症に対しては、そのいずれもが十分でないところに大きな問題点がある。無症状者病原体保有者が一定数存在しているため、感染症対策が非常に難しく、全国の医療施設や老健施設で院内感染・施設内感染、家庭、学校、職場などでの市中感染が相次いで発生していること、また、感染経路として、咳やくしゃみなどだけでなく、会話などから生じるマイクロ飛沫が関与しており、感染予防が困難であることに加え、さらにパンデミックのなかで、変異株が相次いで現われ、伝播性の高い変異株により再び感染拡大が起こることや高齢者や基礎疾患を有している者が重症化し、若年者などでも後遺症がおこることがあるなど、新たな課題や問題が生じている。
今回の新型コロナウイルス感染症パンデミックの出現は、我々人類のすべての領域・分野に大きな影響を与えたが、自然災害の発生の場合と同様に、臨床検査・臨床検査医学の重要性があらためて浮き彫りとなった。
特に、新型コロナウイルス感染症の診断にとって重要なPCR 検査などの遺伝子検査については諸外国に比べ、臨床検査分野での検査機器の導入が遅れたことや遺伝子検査に従事する人材の不足などの課題が明らかとなったことに加え、抗原定性検査や抗原定量検査についても、PCR 検査との検出感度や特異度の比較、検査に用いる臨床検体の評価などが初期には必ずしも十分に行われていなかった。
さらには新型コロナウイルス感染症罹患患者の臨床経過(病態)における各種検査データの解析評価に加え、ワクチン接種による中和抗体産生などの液性免疫機能や細胞性免疫機能の解析の必要性など、今後とも出現するであろう、新たなパンデミックに対し、対応していくべき臨床検査や臨床検査医学分野における基礎的・臨床的研究の新たなる課題が浮き彫りとなり、今後の臨床検査医学の目指すべき方向性が明らかになったことを確信している。
III.ワンヘルスコンセプトとそのコントロールの重要性
現在の感染症を取り巻く問題点としては、感染症が“グローバル化・ボーダーレス化”していることに加え、感染症の“原因微生物が多様化していることが挙げられる。感染症の“グローバル化・ボーダーレス化”については、今回の新型コロナウイルス感染症でも明らかとなったように、人々の交流や交通の発達により、世界のある地域で発生した感染が一気に世界中にひろまり、世界的な感染拡大:パンデミックを惹き起こすこととなる。
また、近年、感染症の原因となる微生物が多様化し、単にヒトからヒトに微生物が感染伝播するだけではなく、動物由来や環境由来の微生物がヒトに感染を起こすことが明らかとなってきた。「ワンヘルス」という考え方は 2004 年米国野生生物保護学会により提唱されたもので、感染症をコントロールしていくためには、これまでのように、単にヒトからのヒトへの微生物の感染伝播だけを考えるのではでなく、動物由来の微生物や環境由来の微生物のヒトへの感染伝播を考えていく必要があるとの考えに基づいている。すなわち、今後、感染症に対応していくためには、これまでの感染症に対する考え方を超えたコンセプト、『ヒトそして動物、環境を包括したワンヘルス』、いわゆる一つの健康という新しい考え方、ニューコンセプトに基づき、対応していくことの重要性が認識されるようになってきている。
事実、新興ウイルス感染症では、2009 年(平成 21 年)に発生した新型インフルエンザはブタのインフルエンザウイルスがヒトに感染を起こし、2012年(平成24年)にサウジアラビアで発生した MERS:中東呼吸器症候群ではラクダからの感染、そして 2014年(平成26年)に発生したエボラ出血熱はコウモリなどの動物が感染源となったことが知られている。また、薬剤耐性菌でも、ヨーロッパでは 2000年代に入り、ブタ由来のMRSA:メチシリン耐性黄色ブドウ球菌のヒトへの感染事例が報告されており、バンコマイシン耐性腸球菌 VRE や、ESBLと呼ばれる第三世代セフェム系抗菌薬に耐性を示す大腸菌が、鶏肉が感染源となり、ヒトへ感染を起こすことも明らかとなってきた。また、東日本大震災などの災害発生時には、環境由来微生物である破傷風菌やレジオネラ菌による感染症が発生するなど、災害時において、環境由来微生物へいかに対応していくかが大きな課題となっている。
このように、ワンヘルスという新たな視点、ワンヘルスの時代において、感染症に対し迅速かつ的確に対応していくために、今後、臨床微生物検査に求められるものは何かを早急に考えていく必要がある。
さらに、臨床微生物学という視点だけでなく、より広い臨床検査診断学の今後のさらなる発展を目指していくためには、「人そして動物、環境を含む ワンヘルス アプローチ」という多面的な視野での対応が不可欠であり、医学領域だけでなく、獣医学領域や環境科学領域などの、様々な分野・領域間で情報の共有化をはかり、共同研究などを含めたコンソーシアム:“アカデミアネットワーク”を構築していく必要がある。
ポストコロナの新たな時代を迎えようとしている今日、“アカデミアヒューマンネットワーク“の構築こそが、臨床検査医学の今後のさらなる発展に大きく寄与する、最も強力なワクチンとなることを最後に強調して、本稿を終える。
JACLaP NEWS 144号 2023年3月掲載
- 投稿者: wp-bright
- 臨床検査医学への提言