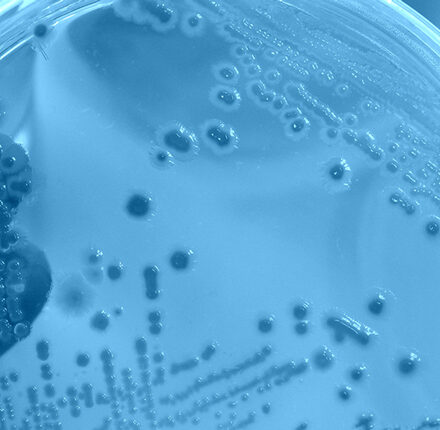臨床検査医学への提言 第三回 熊坂 一成 先生

医療法人社団 愛友会 上尾中央総合病院
診療部臨床検査科科長/感染制御室室長
日本臨床検査専門医会 名誉会員
熊坂 一成
―少し長い前書きー
前会長の登 勉先生、元会長の佐守 友博先生に続き、熊坂が第3回目の「臨床検査医学へのリレー提言」をさせていただく。私は日本臨床検査専門医会(本会)の会長経験者ではない。ご存命の会長経験者である先輩諸氏を差し置いての3番手とはいかがなものかと思い、一度は辞退をした。何より、私は2018年、本会の総会で「今、臨床検査専門医・指導医に求められているもの、ある老臨床病理医 ( 臨床検査専門医 ) の放言~懺悔、省察、苦言そして夢と感謝~」を講演する栄誉を与えられ、「遺言講演」のつもりで臨んだ。
また2019年、第64回中国・四国支部総会での「基調講演:わが国の臨床検査医学-栄枯盛衰そして再興に向けて-」は「遺稿」のつもりで執筆した。後輩の臨床検査専門医の方々に老医の思いの全てを話すことができ、またお伝えしたいことは「臨床病理(現 日本臨床検査医学会誌)」に書き残せたことも辞退した理由である。
しかしJACLaP NEWS 編集主幹の後藤 和人先生から「佐守先生には、次の提言を先生にお願いしたい意図があるようです」とアドバイスもあり、3番手をお引き受けした。
佐守先生は、「前会長はシャープかつジェントルに臨床検査専門医は何をすべきで何が出来ていないかを述懐されていた。同じ内容を私が書いたら、多くの会員が傷つかれ、不快感をいだかれるであろう。しかし「COVID-19の検査に対し臨床検査専門医は何をしていたのか、この疾患の臨床にどう携わってきたのか」を書きたい。」と述べられていた。
登先生、佐守先生がご指摘されているようにCOVID-19のパンデミックでは臨床検査専門医の存在意義、真価が問われ、本会が飛躍できるチャンスであると私も考える。
実際、当院は昨年2月のクルーズ船ダイアモンド・プリンセス号の患者の受け入れに始まり、第5波まで中等症以上の患者を含む多数の患者の入院治療を継続している。臨床検査専門医であり感染症専門医の資格もある私はCOVID-19の外来診療の立ち上げから検査支援体制の構築、院内感染対策さらに各診療科医師からのコンサルテーション、フェイクニュース・インフォデミック対策として最新の正しい情報提供に今も忙殺されている。当院の臨床検査技師諸君もコロナ禍の中、チーム医療のメンバーとしての自覚が高まり、医療技術者として成長された方が多いと自負している。熊坂が前会長のようなジェントルさを持ち合わせていないことを百もご承知である元会長のご指名であってもCOVID-19に関してはこれ以上の記述はしない。その理由は、登先生が憂慮されている医学部における臨床検査医学講座の置かれている危機的状況を打破することがCOVID-19問題より重要と愚考するからである。すなわち本会教育研修委員会が2017年に実施した「医学部における臨床検査医学教育の実態調査」に回答のあった66医学部のうち講座が存在しているのは39(59%) のみであった。残りは検査部や他の研究分野に改組されていた。臨床検査医学教育体制の基本が崩れてきているのである。
―現在,大学で臨床検査医学教育に関わられている会員の方に,そして臨床検査医学講座の教授を目指されている会員以外の方に―
まずは「臨床検査医学講座の在り方と教授の選考にあたって、平成27 年3 月28日」と「大学医学部における臨床検査医学講座の重要性、2018年7月7日」の二つの宣言を熟読していただきたい。その一部を紹介すると、前者では「医療経済が厳しい状況下、高い学識と適切な教育能力に加えて、検査部での医療効率を考えた運営能力を発揮できる人が選ばれるべき。各大学に臨床検査医学講座の設置と責任者として臨床検査専門医である専任教授が選考されることの重要性」が述べられている。後者では、「学生教育の観点から、将来どのような医学の専門領域に進もうとも、臨床検査医学の知識・素養は必要不可欠なものである」ことが記されている。全国の臨床検査医学講座の運営が、この宣言通りにされていたならば、現在の苦境に陥らなかったであろう。現実は、今まで日本臨床検査医学会の会員でなかった方が教授選に立候補し、正規の臨床検査医学(臨床病理学)の教育を受けたことのない臨床検査医学のあるべき姿に疎い教授達が大多数を占める大学では、この二つの宣言が無視される人事がなされる。このような体質の大学では明日の臨床検査医学を背負うべき若い後継者が育たない負のスパイラルに堕いることは必然である。
実際、わが国の臨床検査医学の歴史は苦難の連続であった。57年前に日本の「臨床病理」を開拓されたパイオニア(所属は当時)の小酒井望先生(順天堂大学)、柴田進先生(山口医大)、石井暢先生(昭和大学)、丹羽正治先生(国立東京第二病院)らに、影山圭三先生(慶応義塾大学病理学)を加えた座談会(臨床病理学-その本質と課題-、最新医学。第20巻.第4 号掲載)が開催された。
その中で、影山教授は「若い連中の一般的な傾向を申し上げますと、内科の医者が内科をやめて検査室一本で通すという勇気はないわけです。一方、基礎側からみると例えば生化学の連中が、それじゃ俺が一つ検査部に入って関係領域の仕事を全部やろうという者があればむしろ例外で・・・・」と発言されていた。当時、私は高校生であった。医学生としてパイオニアの先生方のご苦労を全く知らず、米国から帰国して間もない河合忠先生が私にとって臨床検査専門医のロールモデルであった。私は3年間の内科研修の後に、とりあえず数年間のつもりで恩師 土屋俊夫教授が開講した日本大学臨床病理学教室に移籍をした。
日本臨床病理学会に参加して,初めて河合先生のように米国でレジデントとしてmultidisciplineの臨床トレーニングを修了されたような方は極めて少数であることを知った。しかし、影山教授から例外呼ばわりされた諸先生方から直接、薫陶を受けることができたことは極めて幸運であった。
メスを捨てただけの外科医を内科医と呼ばない意味を理解され、わが国の臨床検査医学の再興に向けて心ある会員の方には、前記の拙論(臨床病理67巻7号:728-735)をお読みいただきたい。
―臨床検査医としての将来に不安のある若い先生方に―
2009年、定年まで4年を残して日本大学を退職し、上尾中央総合病院に移籍した。今まで勤務した病院の中で最悪の検査室であった。想像を超えた狭い場所に分析機器が詰め込まれ、採血室の前には患者が溢れ、清潔とは言えない採尿トイレには人の列ができていた。この現状をどうすることもできない劣悪な状態と悲観的に捉えるか、それとも今後、多くの改革を進めるべき組織に招聘された自分は幸運と楽観的に考えるかで、毎日の仕事のやりがい、楽しさが違う。学生時代から哲学者アランを崇拝する私は常に後者である。臨床検査技師は、常勤が52名、非常勤は20名であった。緊急検査以外のルーチン検査も外注する体制にありながら、技師の数を減らすリストラが実施されておらず、技師が若いことは今後の検査室のマネジメント改革をする上で好条件であると考えた。新型インフルエンザの勃発も追い風となり感染症専門医としてのコンサルテーションは順調に伸びたが、臨床検査専門医として院内の認知度を上げるのには若干の時間を要した。日本大学医学部で教育を受けた内科の科長以外のほとんどの医師は、臨床検査専門医を直接利用した経験はなかった。臨床検査技師も、同様にこの専門医に会うのは初めてであった。最初に私に相談を持ちかけた臨床検査技師は輸血検査担当技師であった。次いで血液検査、そして臨床化学、一般検査と順調に検査技師達から毎日の相談件数が増加した。彼ら、彼女らは、今まで相談したくても相談できる医師がいなかったのである。私が輸血検査の基本的知識と技術を習得しており、骨髄像や免疫電気泳動の判定ができ、迅速に臨床検査科から各種報告書を発行し、各診療科の医師から臨床検査に関する各種コンサルテーションを受け、クレームにも対応することを目にした臨床検査技師達から、幸いなことに短期間で私は信頼を得ることができた。臨床検査技師は、誰が「本物」で、誰が「偽物」な臨床検査医なのかを直感的に見抜くのであろう。私をプロフェッショナルな臨床検査医に育てていただいた。故 土屋俊夫先生、河野均也先生そして日本大学病院の多くの臨床検査技師の皆様に、改めて心から感謝をした。
臨床検査医の成長と実力の維持に各分野の優れた専門医をクライアントにすることの重要性は、UCSFであっても、日本大学であっても、埼玉県の医療過疎地にあるこの私立病院であっても変わらない。臨床検査専門医としての真価が問われるのは大学病院を辞めてからである。臨床検査医を目指す若い会員の方々は日本臨床検査医学会の定めた正式のプログラムを遵守して実力をつけられれば,将来に何も憂いはない。
新しい時代の要請に応じることができる臨床検査室を創設するために、赴任直後の5月から11月にかけて土曜日の午後と日曜日を利用して計6回のワークショップ(WS)を開催した。このWSにより新病院検査室にかける皆の「夢」がより現実的なビジョンになり、新病院検査室の設計に反映できた。検査室は以前の3倍のスペースに拡大できた。本会のGLM・WS(Good laboratory management に関するワーク・ショップ)でのチーフプランナーとしての経験が役だった。当院で確認できたことは市中病院では臨床検査医という専門医の存在を知っている職員が、ほぼ皆無であったことと、一方、臨床検査医が病院内で本来業務を全うすることにより多職種の病院スタッフから期待される役割が飛躍的に増したことである。臨床検査医があるべき姿を追求することは何より臨床検査技師に良い影響をもたらす。第11回日本臨床検査医学会 特別例会(2019年)では前川真人教授(浜松医科大学)のご厚情で当院の菊池裕子検査技術科科長(技師長と同じ)が、シンポジウム2(Good Laboratory Management 2019、プレシジョン・ラボラトリーの管理・運営)の講演者としてご指名をいただけた。
―終わりに変えて―
私が医師を目指したのは高校2年生の晩秋の深夜である。父が国立病院の副院長を辞職し開業して2年目、自宅の2階から往診に向かう父を見て、父の手伝いをしなければと思った。結果において晩年、私は年老いた父のクリニックを閉鎖した。
私には孫がいる。孫の主治医は日本大学出身の女性の開業医である。ある時、孫の母親が熊坂の娘であることを知った女性医師は、「臨床病理学実習書」を取り出して、今でもこの実習書が役立っていることを娘に話してくださった。その報告を彼女から受けた私は、恩師の故 土屋俊夫先生、河合先生、河野先生の後を、土屋達行先生(横浜けいゆう病院)、細川直登先生(亀田総合病院)、上原由紀先生(聖路加国際病院)らと一緒に歩んだ、この道が正しかったことを確信できた。老医は、ただ嬉しかった。
JACLaP NEWS 140号 2021年10月掲載
- 投稿者: wp-bright
- 臨床検査医学への提言