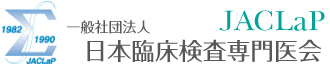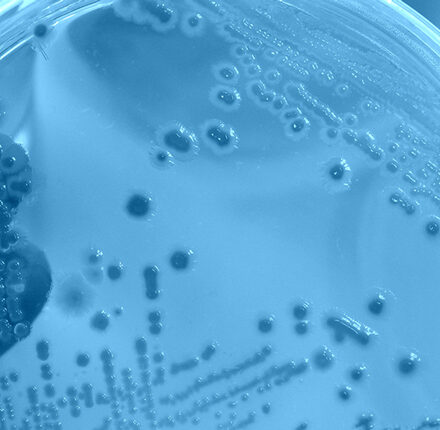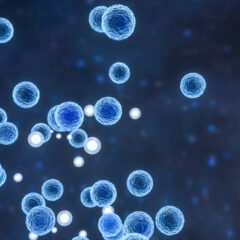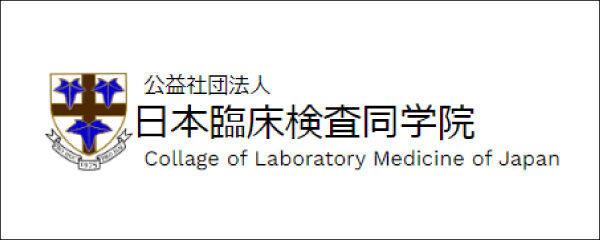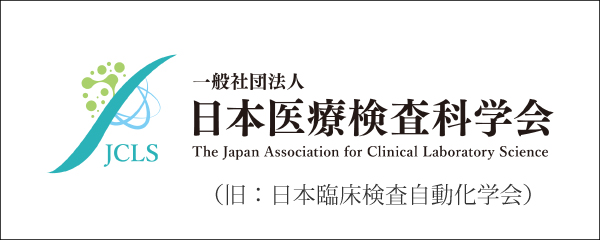臨床検査医学への提言 第六回 濱崎 直孝 先生

九州大学名誉教授
濱崎 直孝
日本臨床検査専門医会の会報(JACLaP NEWS)に寄稿する機会をいただき大変感謝をいたしております。本日は、日本臨床検査専門医会の皆様方への“提言”ではなく新しい検査法の“紹介”をさせて頂きます。
I.エコノミークラス症候群、不育症とプロテイン S 活性測定
2004年10月23日に起こった新潟県中越地震(マグニチュード6.8)では、地震で自宅が崩壊し自家用車中で避難生活をしていた48歳の女性が、避難生活5日目の10月28日に、突然、命を落とした。不幸にも死亡したこの女性は、混雑した避難所を避け自家用車内で避難生活をしており、車中の狭い空間で体を動かさず、また、トイレ使用の頻度を下げる目的で水分摂取を制限していたという。
地震災害現場で救援活動を行っていた井上和男先生(帝京大学・ちば総合医療センター教授;(当時)東京大学病院)はその死因を詳しく調査し、狭い車中での避難生活がその女性の死因であると結論付け“Venous thromboembolism in earthquakevictims.”のタイトルで災害関連の主要な学術誌に論文を発表し、災害時の避難生活の過ごし方に警鐘を鳴らした(Inoue K.Disaster Management Response 2006 年)。この論文は、地震等の自然災害での避難生活中に、肺血栓塞栓症を発症する危険性を指摘した世界で最初の論文である。
新潟県中越地震の被災者 69 名の下肢超音波検査で、22名(32%)が下肢深部静脈に血栓形成があり、その内2名は深部静脈血栓症の症状を呈していた。さらに、1名は肺血栓塞栓症を発症していた。避難所の狭い生活空間で体を動かさず、しかも、充分な水分を摂取しないで避難所生活を送ると肺血栓塞栓症を発症する危険性をこの論文では指摘しており、災害時の被災者の健康管理に重要な指針を示している。
長時間に亘り体動を制限されている状態は避難所生活だけではない。飛行機で長時間旅行したあと、到着地で飛行機から降りて歩き始めた時に急に呼吸困難やショックを起こし死に至ることが、1980 年代後半頃から世間で話題になった。飛行機で長時間狭い座席に座ったままの状態を強いられると、下肢の血流が鬱滞し下肢の深部静脈に血栓ができ(深部静脈血栓症)、目的地に到着しタラップを降りる等で体を動かすことが契機となり、下肢の深部静脈に形成されていた血栓が剥離し肺血管に流れ込み肺血栓塞栓症が発症し、場合によっては死に至るのである。飛行機の狭い座席(エコノミー席)で体を動かさない状態を長く強いられた後に発症することが多いので、象徴的に、《エコノミークラス症候群》と世間的に呼ばれるようになった。
深部静脈血栓症等、静脈血栓塞栓症は、欧米では以前から注目されていた疾病である。特に、膝関節の手術後に高頻度に発症する肺血栓塞栓症は、危険な合併症として、その発症防止対策は臨床の現場では重要な注意点であり良く研究されていた。欧米白人の中には、特に、血栓症を発症しやすい体質の人が一定の割合でいることも知られており、そのような体質を血栓性素因(Thrombophilia)と称していた。その後の研究で、欧米白人で血栓性素因を有する人々は、凝固系第V因子 506 番目のアルギニン(R)がグルタミン(Q)に変異している多型であるFactor V Leiden(R506Q)分子を保因していること、その多型が故に、第 V 因子への凝固制御が掛からなくなり過凝固状態になって血栓症になることが明らかになった(Bertina RM. et al.Nature 1994年)
Factor V Leiden は白人特有の変異であり、今までのところ日本人等アジア人にこの変異を有しているとの報告はない。一方、我々の研究で、日本人の血栓性素因はAPC凝固制御系の活性低下(特に、プロテインS活性低下)であることが判明した(Kinoshita S.et al.Clin Biochem 2005年、Hamasaki N. JThromb Haemost 2012年)。日本人の場合、プロテインS活性が健常人活性の0.78以下になると静脈血栓塞栓症(深部静脈血栓症等)を発症する危険性が非常に高くなることが判明した(Hamasaki N. Sysmex 2011年、Tsuda T. et al. Blood Coagul.Fibrinolysis 2012年)。少ない症例ながら、我々のデータでは、日本人で静脈血栓塞栓症を発症している患者の大半が、プロテインS活性のカットオフ値 0.78以下であった(Tsuda T. et al.Blood Coagul Fibrinolysis 2012年)。すなわち、日本人の主要な血栓性素因は、プロテインS分子異常等に伴うプロテインS活性低下であることが判明した(Hamasaki N. J Throm Haemost 2012年)。したがって、日本人の場合、プロテインS活性測定を行い、プロテインS活性値が基準値の 0.78以下の場合は静脈血栓塞栓症を発症する可能性が高くなるので血栓症発症予防措置を取る必要があると、我々は考えている。
静脈血栓塞栓症は、発症してしまうと生命にかかわる重大な疾病である。これまでは、静脈血栓塞栓症の発症前に、その発症を予知することは非常に難しかった。しかしながら、プロテインS活性の定量測定系が開発できた現在では、プロテインS活性測定値が 0.78未満であると、その個人は、血栓症を発症し易い危険な状態に置かれていると判断できる。そのような個人(患者)には、過剰な血栓形成がおこらないように対処することが必要になる。
話は変わるが、母体のプロテインS活性が低下していると不育症や習慣性流産を起こしやすいという研究発表がある(Rey E. et al. Lancet 2003年、Hojo S. et al. Thromb Res 2008年、Sato Y. et al. J Reprod Immunol 2022年)。その機序は、まだ、明確には解明されていないが、我々は、プロテインS活性低下が原因となって、子宮内の血管での過剰な血栓形成が影響している可能性も捨てきれないと考えている。
我々が開発したプロテインS活性定量測定法(Tsuda T. et al.Blood Coagul Fibrinolysis 2012年)は、静脈血栓塞栓症発症の予兆を的確に知ることができる“新しい検査法”であり、静脈血栓塞栓症の発症防止に有用な臨床検査法である。静脈血栓塞栓症は、血栓が形成されて初めて認識される疾病であり、治療が後手に回ることがある。しかしながら、プロテインS活性定量測定法を活用して個人のプロテインS活性をモニターし、それに対する予防的な医療を行うことで、静脈血栓塞栓症の発症予防や、不育症、習慣性流産の発症予防ができるのではないかと考えている。
プロテインS活性定量測定法は、プロテインS異常症を見出せる検査法であることは言うまでもないが、それに加えて、妊娠、周術期の患者や、長期の避難生活を余儀なくされている等、深部静脈血栓症を発症しやすい環境に置かれている人々の静脈血栓症発症予防スクリーニングには、適切で有力、且つ、簡便な検査法であると思われる。
また、ラットでの予備的な実験であるが、EPA(Eicosapentaenoicacid(20:5 n-3))を事前に経口投与することで、ラット尾部での血栓形成が抑制された実験結果がある(Kuma H. et al. Thromb Res 2013年)。
ま と め
ここで紹介したプロテイン S 活性測定法は、各人の生体内における凝固・凝固制御状態を的確に判断できる。即ち、プロテインS活性測定値が 0.78未満の場合、静脈血栓塞栓症を発症する可能性が高くなる。プロテインS活性測定法が臨床現場で有効に活用され、生命にかかわる重大な疾病である静脈血栓塞栓症の発症予防に活用されることを祈念している。
プロテインS蛋白質測定、および、活性測定は、旧来から保険収載項目になっているので、それらの請求項目で保険請求が可能である。
JACLaP NEWS 143号 2022年10月掲載
- 投稿者: wp-bright
- 臨床検査医学への提言